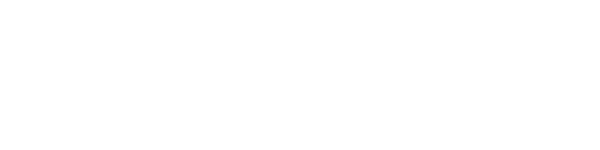当サイトではアフィリエイト広告を使用しています。
フリマ・オークションアプリで不用品を販売する場合に「古物商許可」は必要なのでしょうか。新品だけを扱っているから大丈夫とは限りません。この記事では、どういう場合に古物商許可が必要なのか、どうすれば許可を取れるのかをまとめています。
「古物」は中古品だけじゃない?
「古物商許可」における「古物」とは、中古品だけではありません。法律上の「古物」の定義は以下のとおりです。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物1:一度使用された物品
「一度使用された物品」とは中古品のことですね。中古品はすべて「古物」ですので、販売するためには「古物商許可」が必要です。
かといって、フリマ・オークションアプリで中古品を売る人は全員必要というわけではなく、「業として」行う場合だけです。つまり、売るために継続的に中古品を仕入れたのであれば「業」に該当します。
そうではなく、自分が使うために買ったものを売るというだけならば「業」ではないというわけです。また、ある程度の継続性があれば、それだけでも「業」に該当する可能性があります。
業に該当するかどうかの判断は、管轄の警察署の判断となりますが、「せどり」などの副業目的での販売なら取得しておくべきでしょう。
古物2:使用されない物品で使用のために取引されたもの
これは新品にも、あてはまりますね。
例えば、オークション・フリマアプリに出回っている「新品」は、だれかが自分用に買った未使用のものが多いですね。つまりそれは「使用されない物品で使用のために取引されたもの」に当てはまる可能性があります。
一方、実店舗やAmazon、楽天などから「転売目的」で購入した新品は、「使用のため」に取引されたものではないので、「古物」ではないという考え方も可能です。とはいえ、Amazonや楽天には色々な出品者がいるので、確かなことはいえません。
古物3:1や2に幾分の手入れをしたもの
「幾分の手入れをしたもの」とはつまり、修理・修繕をして、いくら新品に見えるようにしてもダメだよということでしょう。
「古物商許可」はどうやって取るの?
「古物商許可」を取る方法は、主に以下の2つです。
方法1:自分で取得する
警察署に行って、自分で手続きをするという方法です。
警察の担当者が慣れていればいいのですが、ハズレの担当者に当たってしまうと大変ですね。ネット上での販売の場合は、実店舗での中古品販売業と手続き方法が少し異なるので、地方の警察などでは担当者も慣れていない可能性があります。
インターネットなどで、書き方を事前に調べておくといいでしょう。
方法2:代行業者を利用する
古物商許可を取るために「代行業者」を利用するという方法もあります。
代行手数料の相場は4,000円~10,000円程度。さらに法定費用(19,000円)と、住民票、証明書などを準備するために900円程度がかかります。
まとめ
オークション・フリマアプリを、不用品の処分程度に利用するなら古物商許可は不要ですが、副業やせどりなどのビジネス目的で「古物」に該当するものを販売する場合には許可が必要です。